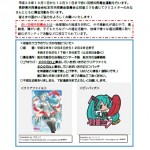音楽文化ホールで、見守り安心ネットワーク活動の推進を図るため、地区社協役員や民生委員、地区ボランティア部会員等522名の方が参加され、「地域の支え合い研修会」を開催しました。
実践活動発表では、信州大学経済学部井上信宏教授を助言者に二つの町会から活動事例を発表いただきました。
第一地区中町三丁目町会の伊東祐次郎町会長さんと中央地域包括支援センター遠山勝也さんは、町内でひとり暮らしの高齢者(女性)の認知症が進んでいるとの相談が近所の方よりあり、日頃から声掛け、見守りを行っていました。町会長、民生委員、家族、医療関係者、ケアマネージャー、ヘルパー、中央包括支援センター職員等関係者が一堂に会して情報を共有し、関係者が個人情報に配慮しながら女性を見守る体制を整え活動を進めることで、町会全体に見守り活動に対する意識付けが進んだことを発表されました。
笹賀地区二美町2丁目町会の村岡康三町会長さんと新田義昭公民館長さんは、安全・安心で住みよいまちづくりを進めるため、高齢者や児童の見守り活動を町会活動の基本としています。
その活動を進めるため、元気に明るく挨拶、向こう三軒両隣での見守り、行事・サークル活動に参加し楽しむことをモットーにしていると話されました。
東日本大震災や6・30松本地震では、町会も大きな被害に遭って地震の恐怖を体験し、日頃からの訓練と備えが必要であると実感したとのことです。そこで、①「命を守る安心ファイル」を作成して全戸に配布し、要援護者に対する隣近所の助け合い体制を整備②子どもを安全に見守るサポーター活動の実施③三世代交流や居酒屋「よってけや」による男性の活動への参加を図るなどの活動を通して、町会の誰でもできるボランティアを進め、住みよい町づくりに取り組まれている事例を発表されました。
続いて、実践活動発表に対しての質疑応答を行ないました。
中町三丁目町会の事例に対する質疑応答
質問
・認知症が進んだことにより、町内の方々との困りごとが増えてきた方に対して、地域の皆さんと専門職の方々が連携して解決していく時に、それぞれの役割分担を考えていたのでしょうか。
回答
・認知症の高齢者を地域で支援するために、関係者が集まり支援会議(打合せ会)を開催したが、初めての試みであったので集まった関係者がどのように関わっているのかを発表し、お互いの分担が確認できました。新たなる課題が出てきた時の土台作りができたので、その時には、関係者が集まり町会のできること、やるべきことと専門家のできること、やるべきことを決めて行う予定です。
質問
・課題の解決に対して、町会長や民生委員だけではなく、隣近所の方々や専門家の方々へどのように声掛けを行なったのでしょうか。
回答
・日頃から人間関係ができていたので、困りごとに対しても隣近所の方々に相談することができました。そして、町会長から包括支援センターへの相談をきっかけとして、関係している専門職の方々も常日頃から問題意識をもっていたので、素直に声掛けができネットワークが組めました。
二美町2丁目町会の事例に対する質疑応答
質問
・町会では、様々な活動に取り組まれていますので、活動がたくさんあると町会役員をやる人が、いなくなるのではないでしょうか。また、たくさん行っている活動の役割分担はどのようにしているのでしょうか。
回答
・様々な町づくり活動や行事を町会役員が楽しんで行っているので、苦も無くできています。また、様々な町会活動だけではなく、PTA活動、長寿会活動など町会内の行事を年度当初に調整し、予定を決め計画に基づいて進めることで負担を軽減しています。
質問
・安心ファイルは、どのように活用しているのでしょうか。
回答
・安心ファイルには、町民の情報や避難場所などの緊急時に役立つ内容が掲載されていますので、情報開示の承諾をいただき定期的にファイルを更新した上で、避難訓練などに持参して確認いただきながら、その必要性を理解してもらっています。
質問
・町会活動への男性の参加が少ない中で、居酒屋「よってけや」の活動は、どのようにして男性の方々が参加し関わっているのでしょうか。
回答
・市の町内公民館長研修会の折に居酒屋の話題が出て、町会長と相談したところ、よいことなので実施することとなりました。お酒を飲み、女性の手作り料理をいただきながら交流することで、男性の参加が増え、若い人と年配の人との交流の場ともなり町内の情報交換の情報の場となっています。
井上先生の実践活動のまとめ
中町三丁目町会の取り組み
1.日常的なお付き合いの延長
2.体験から学ぶ姿勢 課題を抱え込まないでバトンを渡すことが大切
3.専門職との協力関係 個人情報の制約を突破できる人間関係をつくる
4.地域の見守り・支援へ
二美町2丁目町会の取り組み
1.普段からの見守り 町会の目的がはっきりしている。
2.できることから(情報提供) 事後的支援から事前的(予防的)支援へ
3.危機への備え(事前体験) 町会の「常識」をみんなで作る。
4.点の情報を面の支援へ 楽しむことがあなたのできるボランティア
5.喜んでやる、楽しんでやる
地域づくりを進める上でのポイント
今、なぜ地域の支え合いが必要かというと、地域における人間関係、人と人とのつながりが弱くなってきた今だからこそ、困った時に、困らないようにするために、地域の中で協力して支え合う体制づくりが重要となります。
基調説明では、信州大学経済学部教授井上信宏先生が、健康で長生きするためには、心身の健康だけではなく、いくつになっても住み慣れた我が家、我が町で住み続けるために、地域のつながりを取り戻すことを地域住民が共通の課題として考える必要がある、と話されました。
一人暮らし高齢者、高齢者夫婦世帯が急増する中で、当事者が困りごと等を外に向かって発することが少なくなり、地域が気づかない内に複雑化し支援につなげられなくなります。そうなる前に、地域社会の困りごとに気付く役割を担っているのが、町会長と民生委員です。町会長と民生委員が、困りごとを発見して、地域の関係者へつないで地域全体で支援を行うことです。地域の方々には、何ができるのか。何をしなければならないのか。そのためには、様々な手法があるので、その手段を地域の中で話し合って実行に移していくことが大切なことである、と話されました。