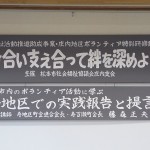「鎌田地区介護者の集い」でリフレッシュ!!
社会福祉協議会鎌田地区支会では、在宅で要援護者を介護している方の負担を少しでも軽減していただければと、「鎌田地区介護者の集い」を開催し、介護技術の参考として、健康相談や尿ケアの説明を行い、またリフレッシュを図るため、落語や手品、音楽鑑賞を実施しています。
本年度第5回目は、1月23日(金)に「清沢まき」さんと「白木まみ」さんが、「美空ひばり」や「都はるみ」のヒットメドレーを披露したり、ザ・ピーナッツ「恋のバカンス、」、小柳ルミ子「瀬戸の花嫁」、ダカーポ「野に咲く花のように」などの歌謡ショー行ないました。
参加された介護者の皆さんも、懐かしい曲に自然と手拍子がでたり、体で調子を取り、楽しいひと時を過ごしました。
その後の介護体験の話しでは、脳梗塞で左麻痺となり、その後体調を崩して寝たきりとなった義母を介護された体験談でした。介護が続き負担から眠れなくなり、医師に相談したところいい加減ではいけないが、いい かげんで、自分を大切にして程々の介護を行うようアドバイスを受けたことで、負担を抱えないようにし、介護をさせて頂くと発想することにより気が楽になったとのことでした。
旦那さんが癌を発病しその後末期がんとなり、自宅療養することとなりましたが、病気にかかった後の夫婦生活は、介護される感謝と介護させてもらっている感謝の生活でしたと話されました。
社会福祉協議会鎌田地区支会では、介護者の方々の一助となればと今後とも介護者の集いを開催しいきますので、ご参加いただければ幸いです。
次回は、3月13日(金)の午前9時30分から「レンゲツツジ」の皆さんによる大正琴の演奏を予定していますので、鎌田地区にお住まいの介護者の方は、お気軽に鎌田地区福祉ひろばへお出かけください。
投稿日:2015年1月26日 カテゴリ:地区活動